
暔岅偼壗傜偐偺撲乮乽扤偑丠乿乽側偤丠乿乽偳偆傗偭偰丠乿乯偵傛傝摫偐傟傑偡丅昁梫側忣曬偑彫弌偟偵偟偐梌偊傜傟側偄偐傜偱偡丅椺偊偽丄乽偦傟偐傜偳偆側偭偨偺丠乿乮And then?乯偲偄偆媈栤偑暔岅偺揥奐傪堷偭傁傞応崌偑偁傝傑偡丅偙偺僞僀僾偺暔岅傪俤丏俵丏僼僅僗僞乕偼 story 偲柤晅偗傑偟偨丅
The king died and then the queen died.
乽墹偑巰偵丄偦傟偐傜彈墹偑巰傫偩丅乿
巕嫙傕偼偠傔偼 story 偱枮懌偡傞偲僼僅僗僞乕偼彂偄偰偄傑偡丅戝恖偺 story 偲偟偰偼楒垽暔岅傪峫偊傟偽傛偄偱偟傚偆丅抝彈偺弌夛偄偑偁偭偨偩偗偱丄偦偺弖娫偐傜撉幰丒娤媞偼乽偙偺愭丄擇恖偼堦懱偳偆側傞偺偩傠偆丠乿偲峫偊傞偼偢偱偡丅摿偵愄偺塮夋偱偼丄庡墘偺抝彈偑弌夛偆応柺偱椉幰偺僋儘乕僘傾僢僾丒僇僢僩偑擖傝傑偟偨偐傜丄娤媞偼偡偖偵偙偺弌夛偄偑塣柦揑側弌夛偄偱偁傞偲偄偆梊姶傪妎偊傞傛偆偵側偭偰偄傑偟偨丅傾僋僔儑儞応柺偱傢傟傢傟偑僴儔僴儔偡傞偺傕乽偙偺屻丄庡恖岞偼偆傑偔摝傟傞偙偲偑偱偒傞偺偩傠偆偐丠乿偲偄偆栤偄偺偨傔偱偡丅偦偟偰丄栤偄偑惗傑傟傞偺偼忣曬偑岻傒偵憖嶌偝傟偰偄傞偐傜偵懠側傝傑偣傫丅
偲偙傠偱乽偦傟偐傜偳偆側偭偨偺丠乿偵娒傫偠偰偄偨巕嫙傕惉挿偟傑偡丅師偺抜奒偱偼乽偳偆偟偰偦偆側傞偺丠乿偲栤偆傛偆偵側傝傑偡丅乽側偤丠乿乮Why?乯偲偄偆栤偄偑摫偔暔岅僞僀僾傪僼僅僗僞乕偼 plot 偲傛傃傑偟偨丅
The king died, and then the queen died of grief.
乽墹偑巰偵丄偦傟偐傜彈墹偑斶偟傒偺偁傑傝巰傫偩丅乿
彈墹偺巰偵偼斶偟傒偲偄偆怱棟揑棟桼偑偁偭偨偺偱偡丅帠崁俙乮墹偺巰乯偲帠崁俛乮彈墹偺巰乯偑宲婲娭學偲偟偰偩偗偱側偔丄場壥娭學偲偟偰偮側偘傜傟偰偄傞揰偱 plot 偼 story 傛傝傕儗儀儖偺崅偄丄傛傝抦揑側暔岅宍幃偩偲峫偊傞偙偲偑偱偒傑偡丅
僼僅僗僞乕偼儈僗僥儕乕晽枴傪偒偐偣偨 plot 暥傕採嫙偟偰偄傑偡丅
The queen died, no one knew why, until it was discovered that it was through grief at the death of the king.
乽彈墹偑巰傫偩丅側偤巰傫偩偺偐偼扤偵傕傢偐傜側偐偭偨丅墹偺巰偵嵺偟偰偺斶偟傒偺偨傔偱偁偭偨偙偲偑敾柧偡傞傑偱偼丅乿
偙偺椺暥偩偗傪傒偰傕儈僗僥儕乕偑忣曬奐帵偺抶墑傪岻傒偵棙梡偡傞巇妡偗偱偁傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅
扵掋暔岅乮Whodunit乯傕儈僗僥儕乕晽枴偺 plot 偺堦庬偲峫偊傜傟傑偡偑丄怱棟揑場壥惈乮Why?乯偽偐傝偱側偔暔棟揑場壥惈乮How?乯偵拲栚偟丄摿偵乽斊恖偼扤偐乿乮Who?乯偲偄偆撲傪尨摦椡偲偡傞憰抲偲峫偊傞偙偲偑偱偒傑偡丅僼僅僗僞乕傪晘煡偡傞側傜偽師偺傛偆側暥傪峫偊傟偽傛偄偱偟傚偆丅
The queen died, it was believed that it was through grief at the death of the king, until it was discovered that she had been poisoned by X.
乽彈墹偺巰偼偼偠傔偼怱楯偵傛傞傕偺偲偝傟偨偑丄乮扵掋偵傛傝乯巰場偑撆嶦偱偁傞偙偲偑摿掕偝傟丄偦偺斊恖傕傗偑偰敾柧偟偨丅乿
偁偲偱傕傒傞傛偆偵丄偼偠傔偺抜奒偱怣偠傜傟偰偄偨偙偲偑嵟廔抜奒偱暍偝傟傞乮傾儕僗僩僥儗僗偺偄偆乽媡揮儁儕儁僥僀傾乿乯偲偄偆偺偑扵掋暔岅偺婎杮峔憿偱偡丅埲壓偱偼傑偢揟宆揑側悇棟傕偺傪儌僨儖偵峫偊傑偟傚偆丅
丂扵掋暔岅偼斊嵾仺憑嵏偲偄偆擇偮偺傾僋僔儑儞偐傜側偭偰偄傑偡丅傆偮偆偼斊嵾峴堊偦偺傕偺偼昤偐傟偢丄偦偺寢壥乮巰懱丄斊嵾尰応乯偩偗偑帵偝傟傑偡丅偮傑傝斊嵾偦偺傕偺偼梊傔夁嫀宍偱採帵偝傟傞傢偗偱偡丅斊嵾偼堦尒偁傝傆傟偨宍傪偲傞応崌傕偁傟偽丄偼偠傔偐傜撲偵曪傑傟偨條憡傪偍傃傞応崌傕偁傝傑偡丅偄偢傟偵偟偰傕丄憑嵏偺慜敿偱偼奧慠惈偺崅偄乮偄偐偵傕偦傟傜偟偄乯梕媈幰憸偑傑偢晜偐傃忋偑傝傑偡丅旐奞幰偵墔傒傪帩偭偰偄偨棎朶側抝丄旐奞幰偵曐尟嬥傪偐偗偰偄偨幰丄摍乆丅偲偙傠偑憑嵏傪懕偗傞偲偳偺梕媈幰偵傕傾儕僶僀偑偁傝丄僔儘偱偁傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅憑嵏偼崱搙偼奧慠惈偼掅偄乮巚偄偑偗側偄乯偑壜擻惈偑攔彍偱偒側偄梕媈幰憸乮椺偊偽丄惔楑寜敀偵尒偊傞恆巑乯偵岦偐偄傑偡丅乽尒偣偐偗偺亀晄壜擻惈亁偑幚嵺偼懚嵼偟側偄乿 乮億僆亀儌儖僌奨偺嶦恖亁乯偲偄偆偺偑扵掋暔岅偺揝懃偱偡丅偦偟偰丄嵟廔揑偵偼巚偄偑偗側偄恖偑恀斊恖乮僋儘乯偱偁傞偙偲偑傢偐傞傢偗偱偡丅丂
丂巹棫扵掋暔偺屆揟乮僐僫儞丒僪僀儖丄傾僈僒丒僋儕僗僥傿乯偱偼丄撲偺庬柧偐偟偼戝抍墌乮d巒ouement乯偱扵掋偑娭學幰傪廤傔偰偍傕傓傠偵側偝傟傞偺偑傆偮偆偱偡丅偦偺偲偒傑偱偼扵掋偺憑嵏忬嫷傗悇棟偖偁偄偼偦偺堦晹偟偐撉幰偵偼抦傜偝傟傑偣傫丅扵掋偼戝抍墌傑偱偼晄摟柧側懚嵼偺傑傑偱丄斵偺巚峫偺僾儘僙僗偼晹暘揑偵偟偐柧偐偝傟側偄偺偱偡丅廋帿妛偱偄偆徣棯朄偑偙偺庬偺悇棟彫愢偺掕宆偲側傝傑偡丅扵掋偺晄摟柧偝傪曐偮偨傔丄傆偮偆扵掋帺恎偼岅傝庤乮僫儗乕僞乕乯偵側傝傑偣傫丅偦偺偐傢傝偵丄撉幰偲扵掋偺娫偺僀儞僞乕僼僃僀僗偲偟偰摫擖偝傟傞偺偑儚僩僜儞揑懚嵼偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
丂儚僩僜儞偼堦斒揑側抦惈傪戙昞偟傑偡丅偟偨偑偭偰丄偟偽偟偽暔帠偺奜尒乮奧慠惈乯偵嵍塃偝傟偑偪偱丄帺暘偺椡偱偼恀幚偵摓払偱偒傑偣傫丅斵偺擟柋偼偁偔傑偱傕儂乕儉僘偵晅偒揧偄丄撉幰偵偐傢偭偰儂乕儉僘傪娤嶡偟丄斵偺尵峴傪撉幰偵揱偊傞偲偄偆傕偺偱偡丅暔岅偵嶲夋偟丄偐偮偦傟傪曬崘偡傞墘媄幰偲岅傝庤傪寭偹偨懚嵼偲偄偭偰傕傛偄偱偟傚偆丅儂乕儉僘偺摿尃揑側榖偟憡庤偱偡偐傜懡偔偺忣曬傪偙偪傜偵採嫙偟偰偔傟傑偡偑丄寛掕揑側忣曬偼傗偼傝戝抍墌傑偱愭憲傝偝傟傑偡丅儚僩僜儞偑偳傫側偵抦傝偨偑偭偰傕儂乕儉僘偼娞怱側偙偲偵偼岥傪暵偞偡偺偱偡丅偮傑傝丄暔岅偺僄僐僲儈乕偐傜偡傟偽丄儚僩僜儞偺懚嵼偼儂乕儉僘偵偮偄偰偺忣曬傪撉幰偵梌偊傞傾儕僶僀偵側偭偰偄傞偲摨帪偵丄偦傟傪幷抐偡傞傾儕僶僀偵傕側偭偰偄傞傢偗偱偡丅偙偺屻幰偺栶妱偵偼撉幰偼偁傑傝婥偑晅偒傑偣傫偑丄偲偰傕廳梫偱偡丅
丂埲忋偺搊応恖暔偺摢偺椙偝傪扵掋暔岅偑憐掕偡傞乽棟憐揑側撉幰乿偺摢擼偲斾傋偰傒傞側傜偽丄儚僩僜儞乮嶲壛宆岅傝庤乯偼撉幰傛傝傕彮偟嬸偐偱丄 儂乕儉僘偼撉幰傛傝傕偼傞偐偵尗偄 偙偲偵側傝傑偟傚偆丅偙傟偼偁偔傑偱傕暔岅僥僉僗僩偑憐掕偡傞撉幰憸乽棟憐揑側撉幰乿偱偁傝丄乽尰幚偺撉幰乿偱偼偁傝傑偣傫丅乽棟憐揑側撉幰乿偲偼丄椺偊偽丄悇棟暔岅偑梡堄偟偰偄傞悌偵偆傑偔傂偭偐偐傞撉幰偺偙偲偩偲峫偊偰偄偨偩偗傟偽寢峔偱偡丅乽尰幚偺撉幰乿偺曽偼偲偄偊偽丄傓偟傠挘傝傔偖傜偝傟偨悌傪偄偐偵弌偟敳偔偐丄僥僉僗僩偺僂儔傪偄偐偵偐偄偰乽棟憐揑側撉幰乿偺愭傪備偔偐偵娭怱傪廤拞偝偣偰偄傞偐傕偟傟傑偣傫丅偙傟傕傑偨丄偙偺庬偺暔岅傪徚旓偡傞偆偊偱僐乕僪壔偝傟偨栶妱偵懠側傜側偄偺偱偡偑丅
丂屆揟揑扵掋暔岅偺僕儍儞儖丒儖乕儖傪嵟弶偵曇傒弌偟偨偺偼僄僪僈乕丒傾儔儞丒億僆偱偡丅亀儌儖僌奨偺嶦恖亁乮1841乯偺岅傝庤偼乽巹乿埲奜偺柤慜傪傕偨偢丄傂偨偡傜僨儏僷儞偺妶桇傇傝傪彂偒婰偟傑偡丅儌儖僌奨偺枾幒偱婲偙偭偨嶦恖偼妋偐偵忢婳傪堩偟偨帠審偱偟偨丅
乽傃偭偔傝偡傞埵偺晀彿偝丄挻恖娫揑側椡丄廱揑側巆媠偝丄摦婡偺側偄巆擡偝丄恖娫惈偐傜揙掙揑偵墢墦偄嫲傠偟偄婏夦側峴堊乵僌儘僥僗僋乶丄偄傠傫側崙偺恖娫偺帹偵奜崙岅偲偟偰嬁偄偨丄偤傫偤傫尵梩偑暦偒庢傟側偄惡乿亀儌儖僌奨偺嶦恖亁
偟偐偟丄堦尒愢柧晄壜擻側弌棃帠傪挻帺慠揑側傕偺偲偼傒側偝側偄偲偄偆寛堄偙偦丄扵掋暔岅偲偄偆怴偟偄僕儍儞儖偑尪憐暔岅偲偄偆媽僕儍儞儖偲逶傪暘偐偮暘悈椾偵側傝傑偡丅
乽傏偔偨偪擇恖偲傕丄挻帺慠揑側弌棃帠側傫偰怣偠傗偟側偄傕偺丅儗僗僷僱乕晇恖曣柡偼桯楈偵嶦偝傟偨偼偢偑側偄丅偙偺嶦恖峴堊幰偼暔幙揑側懚嵼偱偁傝丄偦偟偰暔幙揑偵摝憱偟偨丅乿摨忋
偡傋偰偼帺慠亖壢妛偵傛傝愢柧偑偮偔偼偢偱偁傞偲偄偆嬤戙偺妋怣偑怴僕儍儞儖傪婎慴偯偗傞偺偱偡乮乽尒偣偐偗偺亀晄壜擻惈亁偑幚嵺偼懚嵼偟側偄乿乯丅偝偰丄姶妎偵場傞岆昑乵僪僋僒乶偺媇惖偲側傞偺偼億僆偵偍偄偰偡偱偵寈嶡偱偟偨丅
乽偁偄偮乵償傿僪僢僋寈嶡彁挿乶偼丄懳徾傪偁傫傑傝嬤偔偐傜傒偮傔傞偣偄偱丄傛偔尒偊側偔側傞傫偱偡傛丅乿摨忋
僪僋僒傪柶傟丄乽暘愅揑抦惈乿偵怣傪偍偔僨儏僷儞偑払偟偨堄奜側寢榑偲偼斊恖亖僆儔儞丒僂乕僞儞偲偄偆傕偺偱偡丅偙傟偼尨揷幚偑巜揈偡傞傛偆偵丄乽墡偺榝惎乿偵傑偱帄傞丄椶恖墡偵懳偡傞墷暷偵偍偗傞暥壔僀儊乕僕傪峫偊傞偆偊偱傕婱廳側嵽椏偱偡偑丄偙偙偱偼亀儌儖僌奨偺嶦恖亁偑扵掋暔岅偲偄偆僕儍儞儖偺楌巎偱巆偟偨寛掕揑側堄媊丄偮傑傝塸岅偵 detective 偲偄偆扨岅偑惗傑傟傞慜偵崱擔偺扵掋暔岅乮detective story乯偺曣宆傪憂偭偰偄偨揰傪巜揈偡傞偵偲偳傔偰偍偒傑偟傚偆丅
暔岅偼堦斒揑偵亙寚朢仺寚朢偺夝徚亜偺忬懺曄壔偲偟偰傒傞偙偲偑偱偒傑偡丅偲偙傠偱暔岅偺摦偒偼偐側傜偢峴堊幰偵傛傝攠夘偝傟傑偡偐傜丄忬懺曄壔傪峴堊幰偺梸朷恾幃偵曄姺偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅 偮傑傝丄壗傜偐偺寚朢忬懺偵偍偐傟偨庡懱偑偦偺寚朢傪夝徚偡傋偔偁傞懳徾乮媞懱乯傪梸偡傞偲偄偆恾幃偑暔岅偺婎杮宍偲峫偊傜傟傞傢偗偱偡丅

岮偑妷偄偨恖偼悈傪媮傔傞偱偟傚偆丅暔岅偺悽奅偱偼偦偺懳徾傪庤偵擖傟傞偨傔偵偼傆偮偆偼帋楙乮僥僗僩乯偑偁傝傑偡丅壴嶇栮丄愩愗傝悵側偳偺曬壎傕偺偺亙傗偝偟偝僠僃僢僋僥僗僩亜丄搷懢榊傗棾乮夦暔乯戅帯傕偺偺亙塸梇搙僠僃僢僋僥僗僩亜偑偦偺揟宆偱偡丅
丂扵掋傕偺傪亙庡懱乮梸朷乯媞懱亜偺峔憿恾幃偵曄姺偟偰傒傑偟傚偆丅
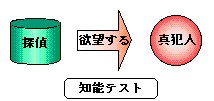
庡懱偼傕偪傠傫扵掋偱丄扵掋偑傕偲傔傞偺偼斊嵾偺恀斊恖偱偡丅屆揟揑扵掋偺応崌丄恎懱揑側傾僋僔儑儞偼擇師揑側傕偺偱偡偐傜丄帺暘偱偼晹壆偐傜堦曕傕弌偢偵寈嶡偺憑嵏僨乕僞偩偗傪傕偲偵悇棟偡傞扵掋傕偄傞傎偳偱偡丅億僆偺応崌偱傕丄亀儅儕乕丒儘僕僃偺撲亁偼尰幚偺嶦恖帠審傪怴暦婰帠偩偗傪棅傝偵夝寛偟傛偆偲帋傒偨椡媄偺夦嶌偱偟偨丅偟偨偑偭偰丄屆揟揑扵掋偑恀斊恖偵摓払偡傞傑偱偺帋楙偲偼偁偔傑偱傕抦擻偺僥僗僩偱偡丅
俙丏俰丏僌儗儅僗偼僾儘僢僾傗僄僥傿僄儞僰丒僗乕儕僆偺搊応恖暔偺峔憿恾幃偵僸儞僩傪摼偰丄庡懱丄媞懱偵偝傜偵墖彆幰丄 朩奞幰 丄庼梌幰丄庴塿幰傪壛偊偰偄傑偡丅
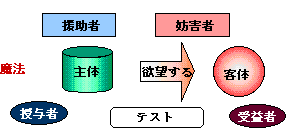 丂
丂偦傟偧傟偳偺傛偆側婡擻傪傕偭偰偄傞偺偱偟傚偆偐丅乽搷懢榊乿傪椺偵偲偭偰傒偰傒傑偟傚偆丅
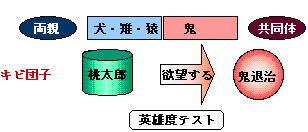
亙傗偝偟偝僥僗僩亜偺寢壥丄搷懢榊偼將丄璩丄墡傪嫙偵摼傑偡偑丄斵傜偑塸梇偺帋楙傪彆偗傞墖彆幰偵側傝傑偡丅傑偨丄塸梇揑峴堊偼朩奞幰傪昁梫偲偟傑偡偑丄婼戅帯偺朩奞幰偲偼偄偆傑偱傕側偔婼偨偪帺恎偱偡丅塸梇偵巊柦傪梌偊偨傝丄偦偺巊柦悑峴傪彆偗傞庤抜傪梌偊傞幰偑庼梌幰偱偡丅乽搷懢榊乿偺応崌丄僉價抍巕乮杺朄偺椡乯傪搷懢榊偵梌偊偨偺偼堢偰偺恊偱偡偐傜丄斵傜偑庼梌幰偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅庴塿幰偼偳偆偱偟傚偆偐丅搷懢榊偺婼戅帯偵傛傝棙塿傪庴偗偨偺偼堢偰偺恊傪娷傓嫟摨懱偲偄偆偙偲偵側傝傑偟傚偆偐丅偙傟偑丄敧枔栰戝幹戅帯偺傛偆偵丄恖恎屼嫙偵側傞偲偙傠偩偭偨墹偺柡傪夦暔偐傜彆偗傞榖偱偟偨傜丄庴塿幰偼傕偭偲偼偭偒傝偡傞偙偲偵側傝傑偡丅
偙偺恾幃傪扵掋暔岅偵摉偰偼傔傞偲偳偆側傞偱偟傚偆丅
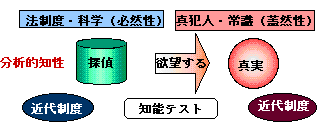 丂
丂丂
丂偙偺屆揟揑儌僨儖偵堘斊偡傞扵掋暔岅傕懡偔偁傝傑偡丅扵掋暔岅偑偄偐偵撉幰傪抦揑偵偁偞傓偔偐傪庡娽偲偟偨僕儍儞儖偱偁傞埲忋丄屆揟揑儌僨儖偺僕儍儞儖朄懃偦偺傕偺傪偄偐偵岻柇偵媆偔偐偲偄偆曽岦傊悇棟彫愢壠偺娭怱偑傓偐偭偰傕壗傜晄巚媍偼偁傝傑偣傫丅
丂埫栙偺僕儍儞儖朄懃傊偺堘斊偲偟偰偟偽偟偽椺偵偩偝傟傞傕偺偵傾僈僒丒僋儕僗僥傿偺亀傾僋儘僀僪嶦恖帠審亁偑偁傝傑偡丅偙偺彫愢偺岅傝庤乽巹乿偼嶦恖偑婲偙傞懞偵廧傓庒幰偱偡丅乽巹乿偺栚傪捠偟偰丄扵掋僄儖僉儏乕儖丒億儚儘偺憑嵏傇傝偑昤偐傟傑偡丅偙偺揰偱偼戝抍墌傑偱晄摟柧側傑傑偱偁傞扵掋偺妶桇傪丄撉幰偲扵掋偺娫偺僀儞僞乕僼僃僀僗偵側偭偰曬崘偡傞儚僩僜儞揑岅傝庤偵嬤偄傢偗偱偡丅偲偙傠偑儚僩僜儞偲寛掕揑側堘偄偑偁傝傑偡丅戝抍墌偱億儚儘偑斊恖偲偟偰巜偟偨偺偼惓偵偙偺乽巹乿偩偭偨偐傜偱偡丅億儚儘偼岅傝庤乽巹乿偵偲偭偰偼媞懱偱偡偐傜丄 億儚儘偑岅傝庤偵偲偭偰乮偟偨偑偭偰撉幰偵偲偭偰傕乯晄摟柧側懚嵼偱偁傞偺偼巇曽偁傝傑偣傫丅抦揑扵掋偼戝抍墌偱偼偠傔偰壖柺傪扙偓幪偰丄摟柧偵側傞偲偄偆偺偑悇棟暔岅偺忢搮偱偁傞偙偲偼偡偱偵巜揈偟傑偟偨丅偲偙傠偑栤戣偼丄杮棃側傜惓捈偵丄拤幚偵帠幚傪曬崘偡傞偼偢偺岅傝庤乽巹乿偑帺暘偺峴摦偺堦晹丄偟偐傕寛掕揑側晹暘傪尵偄棊偲偟偰偄偨偺偱偡丅偙傟傕堦庬偺徣棯朄偲偄偆偙偲偵側傝傑偟傚偆丅
丂岅傝庤偼抦偭偰偄傞帠幚傪乽惓捈偵丄拤幚偵曬崘偡傞乿擟柋傪偍偭偰偄傑偡丅 嫲傜偔偙傟偼扵掋暔岅偵尷傜偢丄撉幰偑暔岅堦斒傪撉傓偲偒偺栙栺側偺偱偡丅撉幰偼岅傝庤偺岅傝庤偲偟偰偺惤堄傪怣偠傞偲偄偆偺偑撉彂偺儖乕儖側偺偱偡丅偱傕丄偙傟偼偁偔傑偱傕栙栺偵偡偓偢丄乽朄揑崻嫆乿偼偁傝傑偣傫丅亀傾僋儘僀僪嶦恖帠審亁偼栙栺傪攋偭偨傢偗偱偡偑丄媡偵偦偺栙栺偺柍崻嫆惈傪朶偄偨偲傕尵偊傑偡丅
丂摨偠傛偆側朄懃攋傝偼幚偼傾僈僒丒僋儕僗僥傿偺嶌昳偵愭棫偮偙偲侾悽婭慜偵偡偱偵徯夘偟偨悇棟彫愢偺晝僄僪僈乕丒傾儔儞丒億僆偵傛傝偡偱偵惉偟悑偘傜傟偰偄傑偟偨丅斵偺抁曇乽偍慜偑斊恖偩乿乮1844乯偺岅傝庤乽巹乿偼斊嵾偑偍偙偭偨儔僩儖僶儔乕偺挰偺乽慞椙側恖乆乿偺帇揰偐傜偡傋偰傪岅傞偺偱偡偑丄 偲偙傠偑幚嵺偼乽儔僩儖僶儔乕偺慞椙側恖乆偲偼堎側偭偨尒抧偐傜乿帠審傪峫嶡偟丄傂偦偐偵憑嵏偡傜偟偰偄偨偙偲傪偡傋偰偑廔偭偨屻偱柧傜偐偵偟傑偡丅扵掋彫愢偲偄偆柤徧偑惗傑傟傞慜偵偙偺僕儍儞儖偺曣宆傪嶌傝忋偘偰偄偨億僆偼傑偨丄偦偺堎宍偺棊偲偟巕偺恊偱傕偁偭偨偺偱偡丅
丂屆揟儌僨儖偵懳偡傞傕偆堦偮偺傾儞僠丒儌僨儖偲偟偰乽孻帠僐儘儞儃乿偑偁傝傑偡丅
丂乽孻帠僐儘儞儃乿偵搊応偡傞乽斵乿偼嶦恖幰偱偡丅偦傟偼僪儔儅偺朻摢偱偡偱偵帵偝傟偰偄傑偡丅乽斵乿偼姰慡斊嵾傪偹傜偭偨抦揑側懚嵼丄僪儔儅偺拞偱嵟傕抦揑側懚嵼偲尵偭偰傕傛偄偐傕偟傟傑偣傫丅斵偺慜偵幏傛偆偵尰傟傞偝偊側偄僩儗儞僠丒僐乕僩傪拝偨抝傪暿偵偡傟偽丅偦偺抝偼崱擔傕傗偭偰偒傑偡丅乽斵乿偑斊偟偨嶦恖帠審偵偮偄偰悇棟傪傂偲偔偝傝挐偭偨屻丄乽斵乿偺斀榑偵帹傪孹偗丄偡偛偡偛偲戅嶶偟傑偡丅僇儊儔偺僋儘乕僘丒傾僢僾偑偲傜偊偨乽斵乿偺栚偵偼埨揼偺怓偑晜偐傃傑偡丅偦偙偵婣偭偨偼偢偺偁偺抝偺惡偑嵞傃暦偙偊偰偒傑偡丅乽斵乿偺娽嵎偟偵堦弖晄埨偑傛偓傝傑偡偑丄偦傟傪偁傢偰偰塀偡傋偔乽斵乿偼岥尦偵旝徫傪偆偐傋傞偱偟傚偆丅乽斵乿偺柤偼嶦恖幰丄晹壆偵栠偭偰偒偰崱巚偄晅偄偨偲偄偆傆偆偵嵟屻偺幙栤傪敪偡傞抝偺柤偼傕偪傠傫孻帠僐儘儞儃偱偡丅
丂偦傟偱偼丄偙偺僪儔儅傪尒傞幰偼堦懱扤偵帺傜傪摨堦壔偝偣傞偺偱偟傚偆偐丠尵偆傑偱傕側偔丄埨揼偲晄埨偺娫傪峴偒棃偡傞帇慄偺帩庡丄偮傑傝嶦恖幰偵偱偡丅暔岅偺朻摢偐傜丄娤媞偼嶦恖幰偲嫟偵偁傝丄嶦恖幰偺怱偺妩傑偱傕尒摟偐偟偆傞摿尃揑側棫応偵抲偐傟偰偄傞偐傜偱偡丅堦曽丄寛偟偰壗傕岅傜側偄帇慄偺帩庡丄孻帠僐儘儞儃偺曽偼娤媞偵偲偭偰偁偔傑偱傕晄摟柧側懳徾偵偲偳傑傝傑偡乮僐儘儞儃傪墘偠傞僺乕僞乕丒僼僅乕僋偺曅栚偼幚嵺偵媊娽偱偡乯丅偙傟偼慞埆偺暔岅偱偼側偔丄岅傞娽嵎偟偲岅傜側偄娽嵎偟偺僪儔儅側偺偱偡丅悇棟暔岅偺忢搮偵偟偨偑偄丄抦揑扵掋偺抦惈偑戝抍墌偱巒傔偰奐捖偝傟傞偲偒傕嶦恖幰偼偗偭偟偰偁偑偄偨傝偼偟傑偣傫丅僐儘儞儃偺曽偱朶椡傪傆傞偆僠儍儞僗傕慡偔偁傝傑偣傫丅朻摢偱峴傢傟偨嶦恖傪彍偗偽恎懱惈偼婓敄壔偝傟丄偐傠偆偠偰乽斵乿偺娽嵎偟偑偦偺巆熸偲偟偰巆傞偩偗偱偡丅岅傜側偄娽嵎偟偺帩偪庡僐儘儞儃偼偟偨偑偭偰晄巰恎乮invulnerable乯偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
|
埲忋偺俁偮偺儌僨儖偼偄偆側傜偽悇棟暔岅偱偁傝丄朻尟偼嶦恖偲偄偆宍偱暔岅偺攚宨乮朻摢丄枊娫乯偱偍偙側傢傟傞偵偡偓傑偣傫丅惓柺偺僪儔儅偼偁偔傑偱傕抦揑側憑嵏丒悇棟偺僪儔儅偱偡丅朻尟偑偡偱偵廔傢偭偰偄傞偨傔丄扵掋偺恎偵婋尟偼敆傝傑偣傫丅屆揟揑扵掋偺応崌丄憑嵏偼庡偵抦揑側僷僘儖偱偁傝丄帺傜偺恎懱傪搎偟偰丄娋悈棳偟側偑傜偡偡傔傞傾僋僔儑儞偱偼偁傝傑偣傫丅偟偨偑偭偰丄僒僗儁儞僗偼側偄偙偲偵側傝傑偡丅 丂扵掋暔岅偼斊嵾仺憑嵏偲偄偆擇偮偺傾僋僔儑儞偐傜側偭偰偄傞偙偲偼偡偱偵傒傑偟偨丅偦偟偰丄扵掋暔岅偵傕扵掋偑恎懱傪夞暅偡傞僞僀僾偺傕偺偑偁傝傑偡丅偙偺応崌丄挷嵏丒憑嵏偦偺傕偺偑廳梫側暔岅梫慺偲側傝傑偡丅扵掋偼摟柧側偄偟敿摟柧偱丄憑嵏偺夁掱偼拃堦丄撉幰乮偁傞偄偼娤媞丒帇挳幰乯偵抦傜偝傟傑偡丅撉幰偼巹棫扵掋乮private eye乯偲偲傕偵憑嵏忬嫷偵偦偺傑傑棫偪夛偆偙偲偵側傝丄忣曬傕儕傾儖僞僀儉偱擖偭偰偒傑偡丅扵掋偼傕偼傗揤嵥偱偼側偔丄偦偺憑嵏丒悇棟偼帋峴嶖岆偺楢懕偱偁傝丄変乆撉幰丒娤媞偺傆偮偆偺摢擼偵嬤偄傕偺偱偁傞偲偝傟偰偄傑偡丅偙偙偱偼丄傾僋僔儑儞傪偲傕側偆扵掋暔岅偺堦僕儍儞儖丄僴乕僪儃僀儖僪傕偺傪傒傞偙偲偵偟傑偟傚偆丅 |
丂憑嵏偵懱傪挘傞僴乕僪儃僀儖僪宆偺扵掋偑傾儊儕僇偱惗傑傟偨偺傕嬼慠偱偼偁傝傑偣傫丅戝搒夛偵廧傒丄幵傪忔傝夞偟偰偄傞偲偼偄偊丄巹棫扵掋偼僇僂儃乕僀偺恑壔偟偨宍側偺偱偡丅惣晹偺峳偔傟幰偨偪偼偄偮偺娫偵偐攚峀傪拝偙側偟丄帺傜傪僊儍儞僌偲徧偟偰偄傑偡丅庰応偼僫僀僩僋儔僽偵曄傢偭偰偄傑偡丅偟偐偟丄朶椡偵偨偊偢偝傜偝傟側偑傜傕寛慠偲偟偨懺搙傪曐偪丄墭傟偨悽奅偵偨傔傜傢偢偵旘傃崬傒側偑傜傕偳偙偐偵惔偄嵃傪塀偟懕偗傞偲偙傠偼僇僂儃乕僀傕巹棫扵掋傕曄傢傝傑偣傫丅
乽僞僼偱側偗傟偽惗偒偰偄偗側偄丅傗偝偟偔側偗傟偽惗偒偰偄傞帒奿偼側偄丅乿儗僀儌儞丒僠儍儞僪儔乕偺惗傫偩扵掋僼傿儕僢僾丒儅乕儘乕偺戜帉丅
僴乕僪儃僀儖僪扵掋偼扵掋暔岅傪朻尟暔岅偵偮側偖僸乕儘乕偲偄偊傑偟傚偆丅
丂傾儊儕僇偺侾俋俁侽擭戙乮俼丏僠儍儞僪儔乕偺悽奅乯傪侾俋俈侽擭戙偺帇揰偱嵞尰偟傛偆偲偟偨塮夋 亀僠儍僀僫僞僂儞亁 乮億儔儞僗僉乕娔撀丄1974乯偺庡恖岞僕僃僀僋丒僊僥傿僗乮俰丏僯僐儖僜儞乯傕偦偺堦恖偱偡丅僒儉丒僗儁乕僪傗僼傿儕僢僾丒儅乕儘乕偲堎側傝丄僊僥傿僗偼嬥偵側傞棧崶栤戣傪庡偵埖偄丄塇怳傝傪偒偐偣偰偄傑偡丅偦偙傊儈儏儗僀晇恖偲柤忔傞彈惈偐傜晇偺慺峴挷嵏傪埶棅偝傟傑偡丅庒偄彈惈偲偺枾夛傪側傫偲偐幨恀偵偲傝晇恖偵搉偟偨偲偙傠丄偦偺幨恀偑悢擔屻僑僔僢僾帍偵岞昞偝傟偰偟傑偄丄偝傜偵偦偺屻丄儈儏儗僀巵偺巰懱偑儘僒儞僕僃儖僗峹奜偱敪尒偝傟傑偡丅僊僥傿僗偼柇側宱堒偱丄杮暔偺儈儏儗僀晇恖乮僼僃僀丒僟僫僂僃僀乯偐傜晇偺嶦恖帠審挷嵏傪埶棅偝傟傑偡丅埶棅庡偺彈惈偑偆偦傪偮偔偲偐丄埶棅偝傟偨傆偮偆偺挷嵏偑嶦恖帠審偵揥奐偡傞偲偄偆偺偼俢丏僴儊僢僩偺亀儅儖僞偺戦亁埲棃偺忢搮偱偡丅
丂挷嵏搑忋偱丄埶棅庡儈儏儗僀晇恖偲僊僥傿僗偼偍屳偄偵庝偐傟崌偆傕偺傪姶偠傑偡偑丄僴乕僪儃僀儖僪傕偺偺忢偱戝楒垽偵傑偱恑傓偙偲偺側偄扺偄娭學偵棷傑傝傑偡丅僴乕僪儃僀儖僪扵掋偼寛偟偰 I love you.偲偼尵傢側偄偺偱偡丅姶忣傪昞尰偣偢偵丄偟偐傕偦偺懚嵼傪埫帵偡傞偲偄偆偺偑僴乕僪儃僀儖僪傕偺偺儗僩儕僢僋偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
丂挷嵏傪恑傔傞偲帠審偺攚屻偵僟儉寶愝偵偐傜傓棙奞懳棫偑偁偭偨偙偲偑柧傜偐偵側傝丄僊僥傿僗偼偨傃偨傃婋偆偄栚偵偁偄傑偡丅偦偟偰偮偄偵丄儈儏儗僀巵偺尦僷乕僩僫乕偱偁傞抧曽偺戝儃僗乮俰丏僸儏乕僗僩儞乯偵夛偄傑偡丅斵偙偦偼嶦恖帠審偺崟枊偱偁傝丄偟偐傕儈儏儗僀晇恖偑侾俆嵥偺偲偒偵斵彈傪椝怞偟偨幚偺晝恊偱偁傞偙偲傕敾柧偟傑偡丅儈儏儗僀巵偑枾偐偵夛偭偰偄偨庒偄彈惈偲偼儈儏儗僀晇恖偺柡偱偁傞偲摨帪偵枀偱傕偁偭偨偺偱偡丅
丂儈儏儗僀晇恖偲柡傪僸儏乕僗僩儞偺杺庤偐傜媬偄弌偡偨傔儊僉僔僐傊偺扙弌偑寁傜傟傑偡偑丄僊僥傿僗偵偲偭偰偼偄傢偔晅偒偺僠儍僀僫僞僂儞偱壗傕抦傜側偄寈嶡偲僸儏乕僗僩儞堦枴偵慾傑傟傑偡丅偟偐傕僸儏乕僗僩儞偵庤彎傪晧傢偣偨儈儏儗僀晇恖傪寈嶡偼幩嶦偟偰偟傑偄傑偡丅柍椡側僊僥傿僗偵搳偘偐偗傜傟偨摨椈偺乽朰傟偨曽偑偄偄丅偳偆偣僠儍僀僫僞僂儞側傫偩偐傜丅乿偲偄偆戜帉偱塮夋偼廔傢傝傑偡丅
丂慜敿晹偺娚傗偐側僥儞億偲屻敿偺壛懍偝傟偨僥儞億偺僐儞僩儔僗僩偺柇丅拞崙恖掚巘偺孞傝曉偡"Bad for (the) grass" 傗儈儏儗僀晇恖偺壗偐傪塀偟偰偄傞條巕側偳丄屻敿偺戝抍墌偱幚傪寢傇偙偲偵側傞庬乮暁慄乯偑慜敿偱壗婥側偔帾偐傟傑偡丅僥儞億偺壛懍偼僊僥傿僗偑儈儏儗僀晇恖偙偦晇嶦偟偺恀斊恖偲岆夝偟丄寈嶡偵揹榖偟偨帪揰偐傜偼偠傑傝傑偡丅僒僗儁儞僗偵偼帪娫惂尷偑昁梫側偺偱偡丅儈儏儗僀晇恖偺崘敀偵傛傝丄崱傑偱偺抐曅揑忣曬偑偡傋偰恾傪惉偟丄僕僋僜乕僷僘儖偑夝偗偨偲偒丄僊僥傿僗偼崱搙偼寈嶡偲僸儏乕僗僩儞偺庤偐傜晇恖傪庣傜偹偽側傝傑偣傫丅僸儏乕僗僩儞傪憡庤偵恀幚傪朶偔戝抍墌偑扵掋傕偺偺嶌朄偵偟偨偑偄偍偙側傢傟傑偡丅偲偙傠偑丄屆揟揑扵掋傕偺偲堎側傝丄恀幚偺朶業亖巌捈偵傛傞惓媊偺幚尰偲偄偆傢偗偵偼偄偐側偄偺偑僴乕僪儃僀儖僪傕偺偺暥朄偱偡丅僊僥傿僗偼僸儏乕僗僩儞偵偲傜偊傜傟丄儈儏儗僀晇恖偺塀傟傞応強傊埬撪偝偣傜傟傑偡丅偙偺傛偆偵暔岅傪廔斦愴偱壛懍偝偣丄堦嫇偵廔嬊傊岦偐傢偣傞偵偼僊僥傿僗偑寈嶡傊偐偗偨堦杮偺揹榖偑昁梫偩偭偨偙偲偑傢偐傝傑偡丅
丂僴乕僪儃僀儖僪扵掋偼椻傔偰偄傑偡丅偦偺偔偣寣擏偺捠偭偨恖娫偱偡偐傜丄垽偵傕朶椡偵傕敇偝傟傑偡丅扵掋偑椻傔偰偄傞偺偼傑偝偵垽傗朶椡偵懳偟偰丄宱尡偐傜棃傞宱嵪朄懃傪揔梡偟偰偄傞偐傜側偺偐傕偟傟傑偣傫丅妋偐偵僴乕僪儃僀儖僪扵掋偼宱尡偐傜偔傞偲巚傢傟傞椻傔傪昚傢偣偰偄傑偡丅暔帠偺埑搢揑偵埫偄柺傪偡偱偵尒偰偟傑偭偨幰丄恖惗偵懳偟偰偡偱偵戝偒側婜懸傪傕偰側偄幰偺椻傔偨帇慄偑丄偵傕偐偐傢傜偢丄晄巚媍側枺椡傪偨偨偊傞彈惈偑帩偪崬傫偩挷嵏埶棅偵傛傝嵞傃堦弖婸偒傑偡丅朶椡偑偁傆傟傞悽奅偱偺帠審偺挷嵏偼摉慠朶椡傪敽偄傑偡丅恎懱傪搎偟偨挷嵏偺枛丄嶖憥偟偨偐傜偔傝偼夝偗丄攚屻偵傂偦傓夦暔偵偨偳傝拝偒傑偡偑丄僴乕僪儃僀儖僪丒僸乕儘乕偼偦偺朻尟偵傛傝曮暔乮旤彈乯傪妉摼偡傞傢偗偱傕側偔丄傑偨丄朻尟傪捠夁媀楃偲偟偰戝恖偵惉挿偡傞傢偗偱傕偁傝傑偣傫丅斵偼偡偱偵捠夁媀楃傪宱偰偄偨偺偱偡偐傜丄崱搙偺朻尟偼偦偺媈帡懱尡偵偡偓傑偣傫丅屻枴偼憡曄傢傜偢嬯偔丄斵偺朻尟偵傕偐偐傢傜偢悽奅偼憡傕曄傢傜偢埆偵枮偪偨條憡傪掓偟偰偄傑偡丅乮幹懌偱偡偑丄亀僠儍僀僫僞僂儞亁偺寢枛偱埆偑敱偣傜傟側偄偺偼幚偼僠儍儞僪儔乕偺儖乕儖乽嬨偮偺柦戣乿偺俉偵斀偟偰偄傑偡丅摉帪偼攑巭偝傟偰偄傑偟偨偑丄僴儕僂僢僪偺塮椣偲傕偄偆傋偒 僿僀僘丒僐乕僪 乵侾俋俇俉擭攑巭乶偵傕怗傟傑偡丅僊僥傿僗偼傑偝偵尰戙壔偝傟偨僼傿儕僢僾丒儅乕儘乕偩偭偨偺偱偡丅乯
乽懢梲偺岝慄偑巹偺偐偐偲傪偔偡偖偭偨丅娽傪奐偔偲丄偆偡偄傕傗偑偐偐偭偨暽偄嬻偵棫栘偺徑偑偐偡偐偵備傟偰偄偨丅乿俼丏僠儍儞僪儔乕亀挿偄偍暿傟亁
乽晹壆偺拞偵偄偨擇恖偼丄巹偺傎偆傪尒岦偒傕偟側偐偭偨丅傕偭偲傕丄堦恖偼巰傫偱偄偨偺偩偑丅乿俼丏僠儍儞僪儔乕亀戝偄側傞柊傝亁
懳徾傊偺姶忣偼帠暔傪尒傞巇憪丄帠暔偲怗傟偁偆巇憪偵傛偭偰偺傒撉幰偵揱偊傜傟傞偩偗偱偡丅庡娤傪攔偟偨娽嵎偟偺塣摦傪捛偆尰徾妛揑婰弎傪傕巚傢偣傞偙偺怴偟偄暥懱偼亀梄曋攝払晇偼擇搙儀儖傪側傜偡亁乮俰丏俵丏働僀儞乯傪捠偟偰僇儈儏偺亀堎朚恖亁傊偲堷偒宲偑傟丄俀侽悽婭屻敿偺暥妛偺怴偟偄暥朄偺墦場偲傕側傝傑偡丅
乽偪傚偆偳拫崰丄姳偟憪傪塣傇僩儔僢僋偐傜曻傝弌偝傟偨丅慜偺斢丄撿偺崙嫬嬤偔偱旘傃忔傝丄暍偄偺壓偵傕偖傝崬傓偲摨帪偵柊偭偰偟傑偭偨丅僥傿儚乕僫偺挰偱偺嶰廡娫偺偁偲偩偭偨偐傜偁偨傝傑偊偩丅僄儞僕儞傪椻傗偦偆偲楢拞偑幵傪婑偣偨偲偒傕丄偖偭偡傝柊偭偰偄偨丅偦傟偱丄撍偒弌偰偄偨曅懌傪尒偮偗傜傟丄曻傝偩偝傟偨偺偩丅偍偳偗偰傒偣偨偑丄憡庤偼傓偭偮傝偟偰偄偨偺偱丄偍傆偞偗偼枊偵偟偨丅墝憪傪堦杮宐傫偱傕傜偄丄怘偄暔傪扵偟偵曕偒巒傔偨丅亙僣僀儞丒僆乕僋僗亜偲偄偆揦偵峴偒摉偨偭偨偺偼偦偺偲偒偩偭偨丅乿亀梄曋攝払晇偼擇搙儀儖傪側傜偡亁
乽偙偺偲偒堦戜偺僩儔僢僋偑嵔偺壒偲敋壒偗偨偨傑偟偔丄傗偭偰偒偨丅僄儅僯儏僄儖偑乽傗傟傞偐側丠乿偲偒偄偨丅巹偼憱傝弌偟偨丅僩儔僢僋偼傢傟傢傟傪捛偄墇偟丄傢傟傢傟偼偦傟傪捛偭偰撍恑偟偨丅巹偼暔壒偲傎偙傝偵偮偮傑傟偨丅傕偼傗壗堦偮尒偊偢丄僋儗乕儞傗婡夿丄悈暯慄偵梮傞斂拰傗傢傟傢傟偑増偭偰憱偭偨慏懱偺偝側偐偵丄憱傝偨偄偲偄偆柵拑嬯拑側擬忣偩偗偟偐姶偠側偐偭偨丅乿亀堎朚恖亁
丂僴乕僪儃僀儖僪傕偺偼斊嵾傪幚尡幒偐傜楬忋偵搳偘弌偟偨偲偄傢傟傑偡乮乽俢丒僴儊僢僩偼丄斊嵾傪償僃僱僠傾丒僈儔僗偺壴時偐傜庢傝弌偟丄偳傇偺拞偵搳偘崬傫偩乿俼丏僠儍儞僪儔乕乯丅傾儊儕僇幃儕傾儕僘儉偺抋惗偱偡丅僴乕僪儃僀儖僪偲嫍棧傪抲偙偆偲偟偨俰丏俵丏働僀儞偵偟偰傕楬忋偺恖偺暥懱偱彂偙偆偲偟偨偺偱偡丅
乽巹偼僞僼偩偲偐丄僴乕僪儃僀儖僪偩偲偐丄椻崜偩偲偐偄偭偨暥懱傪堄幆揑偵帋傒偨偙偲偼堦搙傕側偄丅偦偺搊応恖暔偱偁傟偽偦偆彂偔偱偁傠偆暥懱偱彂偙偆偲偮偲傔偰偄傞偩偗偺偙偲偱偁傞丅乿俰丏俵丏働僀儞乽巹偺彫愢嶌朄乿
偦傟偱偼僴乕僪儃僀儖僪傕偺偼屆揟扵掋傕偺偲偼傑傞偱暿側扵掋暔岅僕儍儞儖偵擖傟傞傋偒側偺偱偟傚偆偐丅妋偐偵怴暦婰帠偩偗偱斊恖傪墘銏偟傛偆偲偟偨僨儏僷儞乮亀儅儕乕丒儘僕僃偺撲亁乯偲楬忋偱恎懱傪挘偭偨憑嵏偑怣忦偺僒儉丒僗儁乕僪偵嫟捠側惈奿偼尒偄偩偣偦偆偵偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄朰傟偰側傜側偄偙偲偼丄偲傕偵撲夝偒暔岅偵偼曄傢傝側偄偲偄偆揰偱偡丅僴乕僪儃僀儖僪傕偺偺拞偵偼嬌傔偰暋嶨側嬝傪傕偮傕偺偑偗偭偙偆偁傝傑偡丅僴儊僢僩偵偟偰傕僠儍儞僪儔乕偵偟偰傕丄嬝偺廔揰偐傜慿偭偰彂偔偲偄偆乽億僆偺敪尒偟偨媄朄傪揔梡偡傞偙偲傪梋媀側偔偝傟偰偄傞乿乮儃儚儘亖僫儖僗僕儍僢僋乯偙偲偵曄傢傝偼側偄偺偱偡丅
|
扵掋暔岅偼斊嵾幰丄旐奞幰丄扵掋偲偄偆嶰曽岦偺儀僋僩儖傪傕偭偨搊応恖暔孮乮儁儖僜僫乯傪昁梫偲偟傑偡丅偦偺偳傟偐偵帇揰傪掕傔偦偺恎懱惈乮乽惗恎乿乯傪昤偒丄偦偺恎懱惈偵岅傜偣傞偲偒僒僗儁儞僗乮旕寛掕偺帪娫乯偑惗偠傑偡偑丄偦偺嫮搙偑堦斣嫮偄偺偼傆偮偆偼柍岰側旐奞幰偺帇揰傪偲偭偨偲偒偱偡丅偟偐偟丄扵掋偑摨帪偵愽嵼揑側旐奞幰偱偁傞応崌傕偁傝傑偡丅 |
丂乽孻帠僐儘儞儃乿傕悇棟暔岅偺怴僕儍儞儖偵偡偓側偄偙偲偼忋偱帵偟偨偲偍傝偱偡丅偲偙傠偑丄偙偺僪儔儅偺僐乕僪乮暔岅偺宊栺忦崁乯偼庡恖岞偑儅僟儉丒僐儘儞儃偵庢偭偰戙傢傜傟傞傗偄側傗斀揮偟傑偡丅乽儅僟儉丒僐儘儞儃乿偱偼丄孻帠僐儘儞儃偼偨偊偢晇偲偟偰晝偲偟偰尵媦偝傟側偑傜傕丄偄偮傕弌挘偱寛偟偰巔傪傒偣傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅塱墦偺扨恎晪擟幰傪帩偮壠掚偼捈偪偵峌寕偵嶯偝傟偆傞乮vulnerable 側乯懚嵼偲壔偟傑偡丅
傾儅僠儏傾怴暦婰幰偲偟偰憑嵏傪偡傞儅僟儉丒僐儘儞儃偵偼偍傑偗偵彫偝側柡偑偄傑偡丅偙偺柡偼幚偼儚僩僜儞巵偵帡偨愢榖揑婡擻傪傕偭偰偄傑偡丅偮傑傝丄僪儔儅傪尒傞娤媞偺岲婏怱傪戙棟偟丄慺恖扵掋偱偁傞曣恊偺榖偟憡庤偲側傞偙偲偱扵掋偵峫偊偰偄傞偙偲傪岅傜偣傞栶妱偑偦傟偱偡丅儚僩僜儞巵偲堎側傞揰偼扵掋乮儅僟儉丒僐儘儞儃乯偺 旐峌寕惈乮vulnerability乯傪嫮傔傞懚嵼偱偁傞揰偱偡丅儂乕儉僘傕儚僩僜儞傕斊嵾幰偵偹傜傢傟傞偙偲偼偁傝傑偣傫偑丄儅僟儉丒僐儘儞儃偺応崌偼偪偑偄傑偡丅傕偟斊嵾幰偑斵彈偺憑嵏偺恑捇嬶崌傪抦偭偨偲偟偨傜偳偆側傞偱偟傚偆偐丠偍偦傜偔憑嵏朩奞傪偡傞偱偟傚偆丅応崌偵傛偭偰偼婋奞傪壛偊側偄偲傕尷傝傑偣傫丅偙偺偲偒惗偠傞儅僟儉丒僐儘儞儃偺旐峌寕惈乮vulnerability乯傪憖嶌偡傞偺偑僇儊儔丒儚乕僋偱偡丅
僇儊儔偑捛偆偺偼傕偼傗娽嵎偟偱偼側偔丄撪晹偺嬒峵傪攋傠偆偲偟偰偄傞奜晹偱偡丅壠偺拞偵偼曣偲柡偑偄傑偡丅奜偵偼崱傗偙偺堦壠偑幾杺偵側偭偨嶦恖幰偑栐傪挘偭偰偄傑偡丅僪儔儅傪尒傞幰偼偟偨偑偭偰撪偲奜偺椉僒僀僪偐傜偺忣曬偑擖傞偲偄偆摿尃揑側棫応偵堦帪抲偐傟傑偡丅壠偵嬤偯偔嶦恖幰丅偲偙傠偑丄偙偙偱僇儊儔偼嶦恖幰偺摦偒傪捛偆偙偲傪撍慠傗傔傑偡丅壗偐偑婲偙傝偮偮偁傞偲偄偆梊姶傪妎偊傞曣巕丅奜晹偐傜偺忣曬偑堦愗偲偩偊偨娤媞偼曣巕偲偲傕偵奜晹=埆偺曊嵼傪僷儔僲僀傾揑偵梊姶偡傞偙偲偵側傞偱偟傚偆丅忣曬偺採嫙偲偦偺撍慠偺幷抐偑 僒僗儁儞僗 偺忦審偱偡丅抦揑乮摢偱偭偐偪乯扵掋偲堘偄丄恎懱傪傕偭偨扵掋偼偄偮偺娫偵偐愽嵼揑側旐奞幰偲壔偟偰偄傑偡丅恎懱傪傕偭偨扵掋偵傛傞憑嵏偼偦傟帺懱偑朻尟側偺偱偡丅
|
扵掋暔岅偼撲偺採帵偲扵掋偵傛傞撲偺夝柧偱廔傢傝傑偡乮 抦擻僥僗僩 乯 丅偟偐偟丄尰幚偺帠審偼偡傋偰夝寛偝傟傞傢偗偱偼側偔丄柪媨擖傝偡傞帠審傕傕偪傠傫悢懡偔偁傝傑偡丅偦偆偟偨働乕僗偼扵掋暔岅偱埖偆偙偲偼晄壜擻側偺偱偟傚偆偐丅傑偨丄斊恖傪偮偒偲傔傞偲偄偆扨慄揑側暔岅偼乽偁傜備傞斊嵾偼摨掕壜擻側埆恖偵傛偭偰偍偙側傢傟傞乿偲偄偆僀僨僆儘僊乕偵埶偭偰偄傑偡偑丄偦偆偟偨場壥榑揑扨慄惈偵娨尦偟偒傟側偄暔岅偲偄偆傕偺偼側偄偺偱偟傚偆偐丅僂儞儀儖僩丒僄乕僐偼亀僶儔偺柤慜亁偺廋摴巑亖扵掋偵師偺傛偆偵岅傜偣偰偄傑偡丅
傑偨丄恀幚傪捛偆扵掋偺峴堊偑扵掋帺恎偺旈枾偵扝傝拝偒乮僸僢僠僐僢僋亀敀偄嫲晐亁乯丄偝傜偵扵掋帺恎偺攋柵傪傕偨傜偡偲偟偨傜偳偆偱偟傚偆偐乮亀僄儞僕僃儖丒僴乕僩亁乯丅偙偆偟偨乽斀乕扵掋彫愢乿乮僗僥僼傽乕僲丒僞乕僯乯偺椺偺嵟傕屆偔姰帏側椺偼僜僼僅僋儗僗偺亀僄僨傿僾僗墹亁偱偡丅 |
僊儕僔儍斶寑偺柤嶌亀僄僨傿僾僗墹亁乮婭尦慜俆悽婭乯偼撲傪夝偔暔岅偱偡丅偦傟備偊扵掋彫愢偺僾儘僩僞僀僾偵偁偘傞恖傕偄傞傎偳偱偡丅僄僨傿僾僗墹偼偦偺撲偑扨側傞扵掋暔岅偺撲夝偒乮Whodunit乯偵偡偓側偄偲巚偄偙傒憑嵏偺恮摢巜婗傪偲傝傑偡丅偲偙傠偑偦偺撲偺拞怱恖暔乮恀斊恖乯偼斵帺恎偵懠側傜側偐偭偨偲偄偆偳傫偱傫曉偟偑嵟屻偵懸偪庴偗偰偄傑偡丅俀愮擭屻偺僂傿乕儞偱偼堦恖偺儐僟儎恖堛巘偑師偺傛偆偵庡挘偡傞偙偲偵側傝傑偟傚偆丅僄僨傿僾僗偺撲偼幚偼傢傟傢傟偡傋偰偺恖娫偑攚晧偭偰偄傞撲乮嬈乯偱偁傞偲丅偙傟偼 僄僨傿僾僗丒僐儞僾儗僢僋僗 偲柤晅偗傜傟傑偡丅審偺堛巘丄僼儘僀僩攷巑偑憂巒偡傞偙偲偵側傞惛恄暘愅偼偙偺撲傪屄乆偺椺偺偆偪偵夝偙偆偲偡傞憑嵏僾儘僙僗偵懠側傝傑偣傫丅偦傟偱偼崻尮偺斶寑偲傕偄偆傋偒亀僄僨傿僾僗墹亁偲偼偳傫側暔岅側偺偱偟傚偆偐丠僜僼僅僋儗僗偺亀僄僨傿僾僗墹亁傪偲傝偁偘偰傒傑偟傚偆丅
暔岅偑偼偠傑傞俀侽擭傎偳慜丄僥僶僀偺墹儔僀僆僗偵傾億儘儞偺恄戸偑偔偩偝傟偰偄偨丅傗偑偰惗傑傟傞巕嫙偵嶦偝傟傞偲偄偆偺偱偁傞乵恄戸侾乶丅恄戸偺幚尰傪晐傟偨儔僀僆僗偼斳僀僆僇僗僥偲偺娫偵惗傑傟偨巕乮倃乯傪梤帞偄偺庤偵戸偟丄偦偺巕傪巰側偣傞偙偲傪柦偠傞乵crime 1丗巕嶦偟乶丅屻擭丄儔僀僆僗偼嵞搙傾億儘儞偺恄戸傪岊偆偨傔偵係恖偺廬幰偲椃偵偱傞偑丄偦偺搑忋乮嶰嬝偺摴偑崌傢偝傞偲偙傠乯偱嶦奞偝傟傞乵crime 2丗墹嶦偟乶丅堦恖摝偘婣偭偨廬幰偼斊峴偑搻懐偳傕偺巇嬈偱偁偭偨偲崘偘傞丅場傒偵偙偺廬幰偼愭偺梤帞偄偦偺恖偱偁偭偨丅堦曽丄墹傪幐偭偨僥僶僀偵偼怴偨側擄戣偑帩偪忋偑偭偰偄偨丅僗僼傿儞僋僗偑恖乆偵撲傪弌偟丄偦傟傪夝偗側偄僥僶僀恖偺柦傪師乆偲扗偭偰偄偨偺偱偁傞丅偦偙傊捠傝偐偐偭偨椃恖偑僐儕儞僩僗墹億儕儏儃僗偺拕巕僄僨傿僾僗偱偁偭偨丅斵偼僗僼僀儞僋僗偺撲傪尒帠偵夝偒丄僥僶僀傪媬偆丅塸梇偲偟偰僥僶僀偺墹嵗偵寎偊傜傟丄儔僀僆僗偺斳偱偁偭偨僀僆僇僗僥傪嵢偵沇傞丅乵偙偙傑偱偼夦暔傪戅帯偟偨塸梇偑墹偺柡傪沇傞偲偄偆塸梇暔岅偺揟宆乮乽屆帠婰乿偺敧枔栰戝幹戅帯丄乽僩儕僗僞儞偲僀僘乕乿偺夦暔戅帯側偳乯偵嬤偄乶
暯榓側偲偒偑偍偲偢傟丄墹晇嵢偼係巕傪傕偆偗傞丅偦偺屻丄僥僶僀偵嵞傃嵭栵偑偍偲偢傟丄塽昦偲婹閇偵柉偼偁偊偖丅斶寑亀僄僨傿僾僗墹亁偺枊慜偵埲忋偺榖偑偡偱偵婲偙偭偰偍傝丄偡偱偵廫暘偵僗僩乕儕乕偺庬偼帾偐傟偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄枊奐偒偲偲傕偵偼偠傑傞偺偼帾偐傟偨庬偑幚乮斶寑乯偲偟偰寢幚偡傞帪娫揑偵傕嬅弅偝傟偨擹枾側僪儔儅偱偁傞丅偡偱偵帾偐傟偰偄偨庬乮忣曬乯偼夞憐乮僼儔僢僔儏僶僢僋乯偲偟偰寑拞偵寑揑岠壥傪偲傕側偭偰摫擖偝傟傞偙偲偵側傠偆丅偄傛偄傛寑偺偼偠傑傝偱偁傞丅
嵭栵偵懳偡傞懳張偼傾億儘儞偺恄戸傪岊偆偙偲偱偁傞丅僄僨傿僾僗偺埶棅傪偆偗丄媊掜僋儗僆儞偑帩偪婣偭偨傾億儘儞偺恄戸偲偼師偺傛偆側傕偺偱偁偭偨丅乽偙偺抧偵偼傂偲偮偺墭傟偑憙偔偭偰偄傞丅偝傟偽偙傟傪崙搚傛傝捛偄暐偄丄偗偭偟偰偙偺傑傑偦偺墭傟傪攟偭偰丄晄帯偺昦崻偲偟偰偟傑偭偰偼側傜偸乿丅偦偟偰偦偺墭傟偲偼丄僋儗僆儞偺夝庍偵傛傟偽丄愭墹儔僀僆僗偺嶦奞乵crime 2乶偱偁傝丄偟偨偑偭偰崙搚傛傝捛偄暐偆傋偒偼偦偺壓庤恖偲偄偆偙偲偵側傞丅
偐偔偟偰僄僨傿僾僗偼壓庤恖偺憑嵏偵忔傝弌偡丅曽朄偼擇偮丅堦偮偼壓庤恖杮恖偺帺庱丄偁傞偄偼徹恖偵傛傞徹尵乮斊峴偺桞堦偺栚寕幰偱偁傞梤帞偄偼暔岅偺廔傢傝偵傗偭偲搊応偡傞乯丅傕偆堦偮偼栍栚偺梊尵幰僥僀儗僔傾僗偵暦偔偙偲丅尵偄傛偳傓僥僀儗僔傾僗偺岥傪柍棟偵奐偐偣偨偺偼僄僨傿僾僗偱偁傞丅僥僀儗僔傾僗偼僄僨傿僾僗偵搳偘偐偗傞丅乽偙偺抧傪墭偡晄忩偺嵾恖丄偦傟偼偁側偨偩乿乽偁側偨偺偨偢偹媮傔傞愭墹偺嶦奞幰偼丄偁側偨帺恎偩乿乽偁側偨偼偦傟偲婥偯偐偢偵丄偄偪偽傫恊偟偄恎撪偺恖偲丄悽偵傕廥偄岎傢傝傪傓偡傃丄偟偐傕帺暘偺抲偐傟偨塣柦偑丄偳傫側偵偍偦傠偟偄晄岾偱偁傞偐丄偦傟偑偁側偨偵偼尒偊側偄偺偩丅乿乽栚偁偒偵偟偰栍偱偁傞偲偼丄偁側偨偺偙偲偩乿乵徹尵侾乶
偲偙傠偑丄偙偺抜奒偱偼僄僨傿僾僗偼僥僀儗僔傾僗偺尵偆偙偲傪怣偤偢丄僋儗僆儞偺嶔棯偲寛傔偮偗傞丅
擇恖偺拠嵸偵擖偭偨僀僆僇僗僥偼埲慜儔僀僆僗偵壓偝傟偨晄媑側恄戸偺偙偲傪岅偭偨乵徹尵俀乶丅僀僆僇僗僥偲儔僀僆僗偺娫偵惗傑傟偨巕偺庤偵偐偐偭偰儔僀僆僗偑嶦偝傟傞偲偄偆恄戸乵恄戸侾乶偱偁傞丅偲偙傠偑儔僀僆僗偼乽嶰嬝偺摴偺崌傢偝傞偲偙傠乿偱搻懐偺庤偵傛偭偰嶦偝傟偨偺偱偁傝乵crime 2乶丄巕嫙偺曽傕棷傔嬥偱椉骠傪巋偟敳偄偨偆偊偱嶳墱偵幪偰傜傟偨乵crime 1乶偺偩偐傜丄寢嬊恄戸偼摉偰偵側傜側偄偲偄偆偺偑僀僆僇僗僥偺僄僨傿僾僗曎岇榑偱偁傞丅偲偙傠偑丄偙偺榖傪暦偄偨僄僨傿僾僗偼晄埨偵偐傜傟傞丅僀僆僇僗僥偺弎傋傞儔僀僆僗偺奜娤偼僄僨傿僾僗偑埲慜偵楬忋偱嶦傔偨恖暔偵偦偭偔傝偩偐傜偱偁傞丅偙偙偱僄僨傿僾僗偼埲慜偵帺傜摼偨傾億儘儞偺恄戸傪巚偄弌偡丅僐儕儞僩僗偵嫃偨崰丄帺暘偑幚巕偱側偄偲偄偆偆傢偝傪帹偵偟丄偦傟傪妋偐傔偵晪偄偨偲偙傠丄傾億儘儞偺恄戸偑乽帺暘偺曣恊偲岎傢傝丄偦傟偵傛偭偰丄恖乆偺惓帇偡傞偵姮偊偸巕庬傪側偟偰悽偵帵偟丄偁傑偮偝偊丄帺暘傪惗傫偩晝恊偺嶦奞幰偲側傞偱偁傠偆乿偲崘偘偨偲偄偆偺偱偁傞乵恄戸侾乫乶丅僄僨傿僾僗偑椃偵弌偨偺傕偦偆偟偨帠懺傪旔偗傞偨傔偩偭偨偺偩丅偦偙傊僄僨傿僾僗偺幚晝偲偝傟傞僐儕儞僩僗墹億儕儏儃僗偺榁悐巰偑巊幰偵傛傝曬崘偝傟傞丅晝偺巰傪斶偟傒側偑傜傕僄僨傿僾僗偼恄戸偺敿暘乮晝嶦偟乯偼尒帠偵偼偢傟偨偙偲偵埨揼偡傞丅偟偐偟丄偦傟傕偮偐偺娫丄巊幰偼僄僨傿僾僗偺晄埨傪偝傜偵姰慡偵夝偔偨傔丄僄僨傿僾僗偑億儕儏儃僗偺幚巕偱偼側偔丄僉僞僀儘儞偺嶳墱偵偄偨幪偰巕乮棷傔嬥偱椉骠傪巋偟敳偐傟偰偄偨乯偱偁偭偨偙偲丄儔僀僆僗偺壠棃偱偁傞梤帞偄偐傜傕傜偄偆偗偨偲偄偆弌惗偺旈枾傪柧偐偡乵徹尵俁乶丅偦偺榖傪暦偄偨僀僆僇僗僥偼偁傢偰偰憱傝嫀偭偰偟傑偆丅乵偙偙偱巊幰偼僄僨傿僾僗偺晄埨傪彍偔偨傔偵惗偄棫偪偺旈枾傪柧偐偡偺偩偑丄偙傟偑媡岠壥偲側偭偰偟傑偆丅僄僨傿僾僗偺慺惈偺擣抦乮傾僫僌僲乕儕僔僗乯偑摨帪偵嬝偺揥奐傪媡揮乮儁儕儁僥僀傾乯偝偣傞偙偺晹暘傪傾儕僗僩僥儗僗偼亀帊妛亁偺側偐偱崅偔昡壙偟偰偄傞丅乶
寛掕揑側徹恖偑搊応偡傞丅僉僞僀儘儞偺梤帞偄偱偁傞丅偼偠傔偼徹尵傪嫅傫偩抝傕僄僨傿僾僗偵嫼偝傟丄恀幚傪偄偆偙偲偵側傞丅偦偺愄丄梤帞偄偑僐儕儞僩僗偺巊幰偵梌偊偨巕偲偼儔僀僆僗偲僀僆僇僗僥偺巕乵倃乶偱偁偭偨乵徹尵係乶丅乵crime 1乶偼峴傢傟偢丄乵倃乶偼億儕儏儃僗偺梴巕偲側偭偨偺偱偁傞偐傜丄僄僨傿僾僗偙偦乵倃乶偩偭偨偺偱偁傞丅傾億儘儞偺恄戸偼姰帏偵幚尰偝傟偰偄偨偺偱偁偭偨丅
僀僆僇僗僥偼庱傪偮傝丄僄僨傿僾僗傕帺傜偺椉栚傪偔傝偸偔偲偄偆斶嶴側寢枛偱寑偼廔傢傞丅
恄戸偺儊僇僯僘儉偼偦偺椉媊惈偵偁傝傑偡丅恄戸傪暦偒丄偦偺幚尰傪朩偘傞偨傔偵島偠偨庤抜偑幚偼恄戸傪幚尰偝偣偰偟傑偆偲偄偆旂擏側揮搢偙偦恄戸偺栚榑尒側偺偱偡丅晝嶦偟偼丄儔僀僆僗乮晝乯偑恄戸傪怣偠偰僄僨傿僾僗乮巕乯傪乮偙偺悽偐傜乯墦偞偗傛偆偲偟偨寢壥偱偁傝乵晝偑扤偐傢偐傜側偔側傞乶丄傑偨丄僄僨傿僾僗偑恄戸傪怣偠偰曻楺偺椃偵偱偨寢壥偱傕偁傝傑偡乵晝偵嵞傃嬤偯偔乶丅僗僼傿儞僋僗偺撲傪夝偄偨僄僨傿僾僗偑傾億儘儞偺恄戸偲偄偆撲偵東楳偝傟傞偺偼斶寑偺尩枾側儊僇僯僘儉偺昁慠揑側寢壥側偺偱偡丅傾儕僗僩僥儗僗偼斶寑偑乽梊婜偵斀偟偰丄偟偐傕場壥娭學偵傛偭偰婲偙傞応崌傕偭偲傕岠壥傪偁偘傞乿偲弎傋偰偄傑偡偑乮亀帊妛亁戞侾侾復乯丄恄戸偺椉媊惈偙偦堄奜惈偲場壥惈偲偄偆擇廳偺岠壥傪幚尰偡傞摿尃揑側攠懱偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
堦曽丄壓庤恖憑嵏偺暔岅偱偁傞埲忋丄亀僄僨傿僾僗墹亁偼傑偨扵掋暔岅偱傕偁傝傑偡丅徹恖偑師乆偲搊応偟丄僄僨傿僾僗偺慜偱偲偒偵寵乆側偑傜徹尵偡傞偲偄偆揰偱偼丄嵸敾寑偲偄偭偨曽偑惓妋偱偟傚偆偐丅梊尵幰僥僀儗僔傾僗偵傛傞斊恖亖僄僨傿僾僗愢偵偼崻嫆偑偁傝傑偣傫偑丄扵掋僄僨傿僾僗偺廸晝僋儗僆儞偵傛傞杁棯愢傕偦傟埲忋偵崻嫆偑偁傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅僀僆僇僗僥偼僄僨傿僾僗曎岇偺偨傔偵丄恄戸偺撪梕偲儔僀僆僗嶦奞偺忬嫷偺晄堦抳傪徹尵偟傑偡偑丄偙傟偼暋悢偺搻懐偵傛傞偲偄偆晹暘傪彍偗偽僄僨傿僾僗偺僼儔僢僔儏僶僢僋偲偐偊偭偰堦抳偟偰偟傑偄傑偡丅僐儕儞僩僗偺巊幰偑僄僨傿僾僗曎岇偺偨傔偵採弌偟偨怴徹尵偼丄嵟屻偺徹恖僉僞僀儘儞偺梤帞偄偵傛傝棤晅偗偝傟丄偝傜偵暋悢搻懐愢偑斲掕偝傟傞偙偲偵傛傝丄僄僨傿僾僗亖恀斊恖愢偑徹柧偝傟傑偡丅偙偆偟偨徹恖偺弌偟曽傕僜僼僅僋儗僗偼岻傒偱偡丅傑偝偵乽梊婜偵斀偟偰丄偟偐傕場壥娭學偵傛偭偰婲偙傞応崌傕偭偲傕岠壥傪偁偘傞乿偲偄偆傾儕僗僩僥儗僗偺斶寑棟擮偵姰帏偵崌抳偟偰偄傑偡丅扵掋偑恀幚傪朶偔傋偔儀乕儖傪堦枃堦枃庢傝嫀傞偲嵟屻偵偼扵掋偙偦偑恀斊恖偱偁偭偨偲偄偆嬃偔傋偒帠幚偑尰傟傞暔岅丄恀幚扵媮偺巇憪偑扵掋偺帺屓攋柵傪傕偨傜偡暔岅傪僗僥僼傽乕僲丒僞乕僯偼乽斀乕扵掋彫愢乿偲柤晅偗傑偟偨偑丄亀僄僨傿僾僗墹亁偙偦斀乕扵掋暔岅偺嵟崅寙嶌偲怽偣傑偟傚偆丅
|
悇棟彫愢偺嶰杮拰偼扵掋丄旐奞幰丄斊恖偱偡丅僒僗儁儞僗傕偺偱偼扵掋偲旐奞幰傪摨堦恖暔偑墘偠傞偙偲偑傛偔偁傝傑偡乮椺丗僸僢僠僐僢僋丄儃儚儘乕丒僫儖僗僕儍僢僋乯丅偲偙傠偱丄扵掋亖旐奞幰亖斊恖偲偄偆嶰埵堦懱偺悇棟彫愢傪峫偊傜傟傑偡偐丅丂 |
丂乽巹偑偙傟偐傜暔岅傞帠審偼岻柇偵偟偔傑傟偨嶦恖帠審偱偡
丂丂巹偼偦偺帠審偱扵掋偱偡
丂丂傑偨徹恖偱偡
丂丂傑偨旐奞幰偱偡
丂丂偦偺偆偊斊恖側偺偱偡
丂丂巹偼巐恖慡晹側偺偱偡
丂丂偄偭偨偄巹偼壗幰側偺偱偟傚偆乿
偲偄偆僉儍僢僠丒僐僺乕傪傕偮悇棟彫愢偑 僙僶僗僠儍儞丒僕儍僾儕僝 嶌亀僔儞僨儗儔偺悌亁偱偡丅
丂暔岅偼乽巹乿偺栚妎傔偐傜巒傑傝傑偡丅栚妎傔偼忢偵柍偐傜偺抋惗偺僪儔儅偱偡丅乽崱乿偑偄偮側偺偐丄乽偙偙乿偑偳偙側偺偐丄乽巹乿偑扤側偺偐丅栚妎傔偺僾儘僙僗偲偼偙偆偟偨懚嵼偵偮偄偰偺崻尮揑側栤偄偵懳偡傞摎偺柾嶕偵懠側傝傑偣傫丅亀僔儞僨儗儔偺悌亁偺乽巹乿偺応崌丄偙傟傜偺栤偄偼摿偵愗幚側堄枴傪帩偪傑偡丅側偤側傜丄斵彈偼偁傞帠審偺偨傔偵慡恎偵壩彎傪晧偄丄偟偐傕婰壇傕憆幐偟偰偄傞偐傜偱偡丅帠審乮壩帠乯偺旐奞幰偲偟偰傑偢搊応偡傞乽巹乿偼丄惍宍庤弍偵傛傝恎懱傪怴偨偵憂憿偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅傑偨乽巹乿偺夁嫀傪嵞峔惉偡傞偙偲偵傛傝乽巹乿偺傾僀僨儞僥傿僥傿傕憂憿偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅偟偐傕寛掕揑側忣曬偑寚偗偰偄傑偡丅巹偼帠審偺応偵嫃崌傢偣偨僪乮僪儉僯僇丒儘僀乯側偺偱偟傚偆偐丄儈乮儈僔僃儖丒僀僝儔乯側偺偱偟傚偆偐丠傑偨丄壩帠応偵巆偝傟偨從巰懱偺恎尦偼僪側偺偱偟傚偆偐丄儈側偺偱偟傚偆偐丠
丂扵掋偲側偭偨乽巹乿偵傛傞傾僀僨儞僥傿僥傿扵偟偑巒傑傝傑偡丅恎懱偲婰壇傪憆幐偟偨偺偱偡偐傜丄帺傜偺傾僀僨儞僥傿僥傿偲帠審偱偺栶妱偵偮偄偰偺忣曬尮偼偡傋偰懠幰偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅懠幰偲偄偆嬀傪捠偟偰偺傒帺暘偺傾僀僨儞僥傿僥傿傪嵞峔惉偱偒傞偲偄偆偺偑偙偺暔岅偺巇妡偗乮傢側乯偱偡丅
丂儈偺楒恖偼乽巹乿偑儈偩偲尵偄傑偡丅嵟廳梫偺徹恖丄儈偺屻尒恖偱偁傞僕儍儞僰丒儈儏儖僲偼乽巹乿偑僪偩偲偄偄傑偡乮乽偙傫偽傫傢丄僪乿乯丅僕儍儞僰偵傛傞夁嫀偺嵞峔惉偼嫲傞傋偒傕偺偱偟偨丅儈偲僪偺娭學偑庡恖偲搝楆偺偦傟偱偁傝丄僕儍儞僰偲僪偺娫偱儈傪嶦偡寁夋偑偁偭偨丅偟偐傕儈僪儔偍偽偝傫偺堚嶻憡懕偺偨傔丄嶦奞屻僪偑儈偺傆傝傪偡傞偙偲傑偱寛傑偭偰偄偨丄偲偄偆偺偱偡丅偟偨偑偭偰丄偙傟偐傜傕巹亖僪偼儈傪墘偠懕偗傞傛傝懠偼側偄偺偩偲乮乽偄偄偙偲丄偁側偨偼儈僢僉乕傛乿乯丅
丂師偵怴偨側徹恖丄梄曋攝払晇偑搊応偟傑偡丅斵偵傛傟偽巹偼儈偱偁傝丄斊嵾寁夋傪抦偭偨巹偑偦偺僂儔傪偐偒丄愽嵼揑旐奞幰偐傜嶦恖幰偵側偭偨偲偄偆偺偱偡丅巹亖儈偑僪傪嶦偟偨偺偩偲梄曋嬊堳偼備偡傝傑偡丅傑偨丄僪偺楒恖傕偁傜傢傟丄傗偼傝巹亖儈偑僪傪嶦偟偨偺偩偲尵偄傑偡丅側偤側傜乽堚嶻憡懕恖偼僪側傫偱偡乿丅
丂偙偆偟偰傾僀僨儞僥傿僥傿扵偟偼怳傝弌偟偵傕偳傝傑偡丅乽巹乿偼儈側偺偐丄儈傪墘偠傞僪側偺偐丅巹偼壛奞幰側偺偐丄旐奞幰側偺偐丅乽巹偼扤偐尵偭偰傛丄僕儍儞僰乿丂偟偐偟丄埲忋偺僨乕僞偐傜乽巹乿偺傾僀僨儞僥傿僥傿傪墘銏偱偒側偄傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅乽巹偑敀偄岝偺壓偱栚傪偁偗偨偲偒偐傜丄僕儍儞僰偼巹傪僪偲傒側偡桞堦偺恖偩偭偨丅巹偺夛偆恖乆偼丄巹偺楒恖傗丄晝傑偱丄巹傪儈偲巚偭偨丅側偤側傜偽巹偼儈偩偐傜偩丅乿
乽巹乿偼偄傢偽儕僙僢僩偝傟丄僛儘偐傜傑偨巒傔側偗傟偽側傜側偄僎乕儉偺暿徧偱偁傝丄僎乕儉傪捠偠偰嶌傝忋偘傞傋偒懳徾偱傕偁傝傑偡丅梊尵幰僥僀儗僔傾僗偑僄僨傿僾僗偵搳偘偮偗偨偙偲偽乽栚偁偒偵偟偰栍偱偁傞偲偼丄偁側偨偺偙偲偩乿偼亀僔儞僨儗儔偺傢側亁偺乽巹乿偵傕摉偰偼傑傝傑偡丅懠幰偵偼尒偊傞帺暘偺巔偑尒偊側偄偺偼乽巹乿偩偗側偺偱偡丅憑嵏曽朄傕僄僨傿僾僗偺応崌偲摨偠偱丄暋悢偺徹恖偵栤偆傛傝懠偵偁傝傑偣傫丅徹尵偺娫偺柕弬傪夝偒丄乽巹乿偺恀偺傾僀僨儞僥傿僥傿傪柧傜偐偵偡傞恀偺徹尵傪尒嬌傔傞偲偄偆扵掋亖敾帠偺悇棟椡偑昁梫偲側傝傑偡丅斀乕扵掋暔岅偱憑嶕偡傋偒恀幚偲偼巹亖扵掋偺恀偺傾僀僨儞僥傿僥傿偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
|
丂扵掋暔岅偵傆偝傢偟偄斊嵾偑嶦恖偱偁傞偙偲偼懡偔偺恖偑巜揈偟偰偄傑偡丅嶦恖偼棟榑揑偵偼嶦恖幰丄旐奞幰丄扵掋偺嶰偮偺堎側傞棫応偐傜岅傝摼傑偡丅屆揟揑側暔岅偼扵掋乮偁傞偄偼扵掋偵嬤偄埵抲偵偄傞恖乯偺棫応偐傜岅傜傟傑偟偨丅乽斊嵾偺暔岅偼丄傗偼傝扵掋偺懁偐傜尒傞偺偑堦斣挱傔偑偄偄乿乮俤丏俵丏儘儞僌乽斊嵾偲扵掋乿俫丏僿僀僋儔僼僩曇亀悇棟彫愢偺旤妛亁尋媶幮乯偲偄偆峫偊曽偑偆傑傟傞強埲偱偡丅偟偐偟丄幚嵺偵偼斊嵾傪斊嵾幰偺棫応偐傜昤偔暔岅偵傕悢懡偔偺柤嶌偑偁傝傑偡丅偄傢備傞弮暥妛偵偼傓偟傠斊嵾幰偺帇揰偐傜彂偐傟偨傕偺偺曽偑懡偄偔傜偄偱偡丅亀嵾偲敱亁亀堎朚恖亁亀梄曋攝払晇偼擇搙儀儖傪側傜偡亁亀懢梲偑偄偭傁偄亁亀巰孻戜偺僄儗儀乕僞乕亁亀嶦恖偺壞亁丅斊嵾幰偺暔岅偵偮偄偰偼暿偺儁乕僕偑昁梫偵側傞偱偟傚偆丅 |